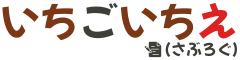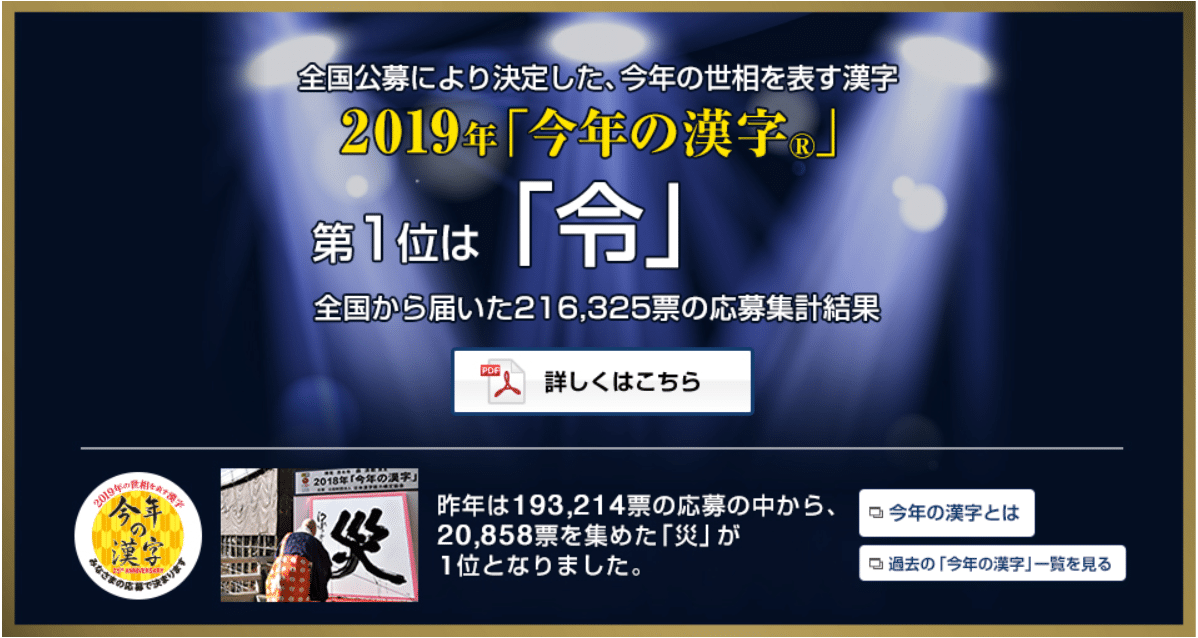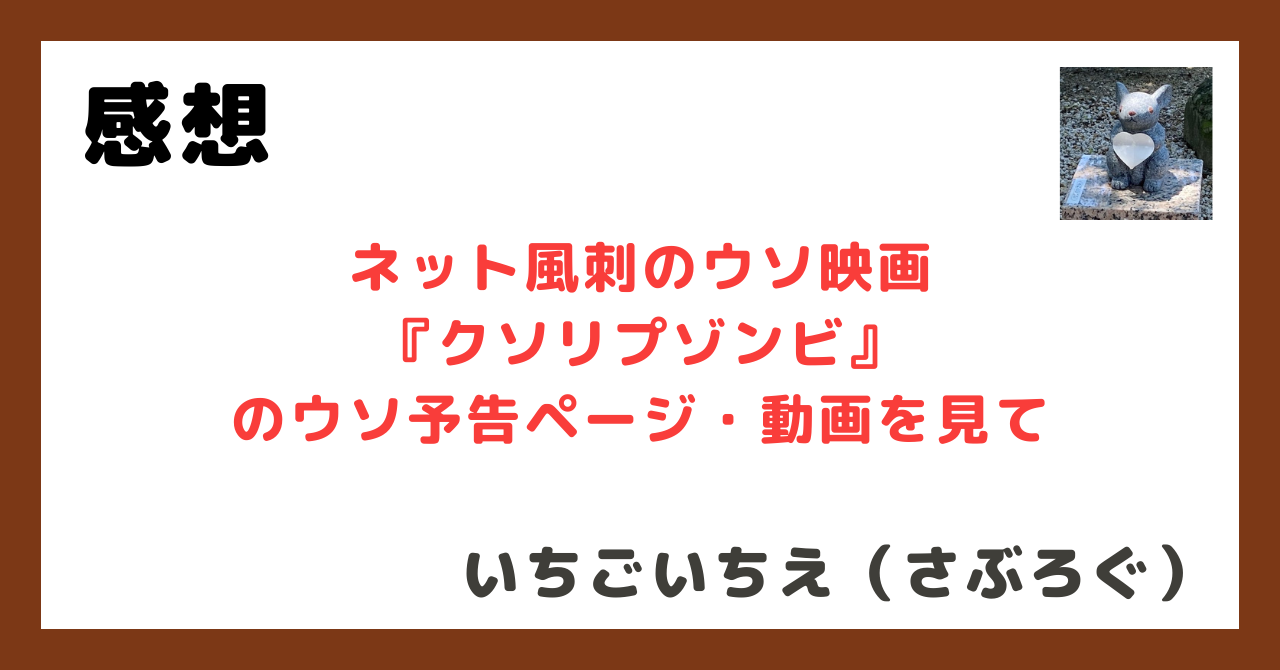先日、播但線を唯一走行する定期特急「はまかぜ」号に乗車してきたので、そのことについて簡単に記すこととしたい。
列車概要

大阪駅から、JR神戸線、播但線、山陰本線を経由し、香住駅、浜坂駅、鳥取駅までを結んでいる特急列車。現時点では定期で3往復運行されている。なお、冬場のかにシーズンにおいては、「かにカニはまかぜ」としてもう1往復運行される。
運行区間は、香住駅までで1往復、浜坂駅まででもう1往復、鳥取駅まででさらにもう1往復といった塩梅となっている。ちなみに「かにカニはまかぜ」は浜坂駅までで1往復である。また、原則は3両編成での運行であるが、冬場や多客期を中心に、6両に増結されることもある。
所要時間は、浜坂駅から姫路駅まででおよそ2時間半。そこからさらに1時間程度かけて、終点の大阪駅に到着する。なお、大阪以遠から鳥取駅まで行く場合は「スーパーはくと」号を利用したほうが早く着く。また、城崎温泉駅や豊岡駅まで行く場合も、大阪や京都からの乗車の際は「こうのとり」や「きのさき」を利用するのが早い。
特急料金は「B特急」が適用されるため、若干安めではある。
走行区間内は電化区間と非電化区間が入り混じっているため、用いられるのは「JR西日本189系気動車」。2010年以前は国鉄時代の車両「国鉄181系気動車」が用いられていたが、同年11月7日以降、新型車両に置き換えられ、国鉄車両は運用から退いていった(なお、国鉄181系気動車が定期運行で用いられていた最後のケースでもある)。
なお、この特急は姫路駅でスイッチバックを行うため、座席を逆方向に回転させる旨の放送が流れる。
乗車状況

前々から気になっていた「はまかぜ」号に乗車することがかなった。今回乗車したのは4号(浜坂駅始発)であり、平日の昼間ということもあってか、始発駅の時点では自由席においても乗客はあまり見られなかった。
乗客が入るようになったのは竹野駅から。この時点でもまだまだ空席が目立っていたが、城崎温泉駅、豊岡駅といった但馬地区の中心部を通ってからは、いよいよ席に人が埋まりだしてゆく。
途中、八鹿駅や和田山駅でいくらか人の動きはあったものの、依然として乗車率はそこそこ高い塩梅(おそらく70%くらいはあったのではないだろうか)。和田山駅から播但線に入ったところでは人の動きがほぼなくなってゆく。
姫路駅に到着すると、私も含めて大勢の乗客が降りていってしまった。当駅では新たに乗車する客はいないに等しく(新快速があるから当然ではあるのだが・苦笑)、車内はおそらくガラガラになっていたことだろう。
乗車した感想

「はまかぜ」号は、兵庫県の山陰西部と山陽部各都市を結んでいるところが大きいように思う。言い換えれば、「こうのとり」や「きのさき」だけでは賄いきれない部分をカバーしているということだ。
「播但線内を唯一走る定期特急」という謳い文句から、当初はその区間内でも需要があるものと思っていた。しかし、実際に乗車してくる人はほとんどいなかった。逆に、和田山駅以遠、但馬地区から乗車してくる客が結構いて、その部分での需要の方が大きいのではないか、と感じたのである。
大阪駅発着だったり、1往復分が鳥取駅まで運行されたりするのは、おそらく運用上の都合だろう。わざわざ好き好んで鳥取から大阪まで「はまかぜ」で行くなど、よほどのマニアでもなければあり得ない(私のことだが)。
実は、浜坂駅からでも、あらかじめ鳥取駅まで行ってから「スーパーはくと」号に乗り換える方が姫路駅や大阪駅に早く着く場合もあるし、始発駅乗車での「はまかぜ」号の利点としては「乗換なしで行ける」というところくらいである。乗車時点でガラガラだったのは、そういう側面もあるだろう(単に周辺の人口が少ないというのもあるだろうが)。
鳥取、兵庫、大阪の1府2県を走行する列車ではあるものの、利用客はもっぱら兵庫県内の移動が目的であるという、珍しいタイプの特急列車である――このことだけは、今回の乗車でよく分かった。
余談:「余部橋梁」について
この節の冒頭にある写真は、餘部駅を通過した辺りで撮影した車窓だ。付近にある「余部橋梁」は撮影スポットとして非常に有名であり、車窓からの眺めも大変良い。香住駅や浜坂駅までアクセスすることがあれば、目に焼き付けておくことをオススメする。
私もいつか、餘部駅に直に行ってみたいものである。
「国鉄181系気動車」時代のはまかぜ号(2020/05/04追記)

上述の「国鉄181系気動車」時代の「はまかぜ」号、実を言うと2008年に撮影していたのであった。この写真ファイルが見つかったので、当記事にも掲載することとした。
撮影当時の姫路駅は、現在と違い、播但線や姫新線のホームがまだ地上に存在していた。これらのホームも高架化された今となっては、車両・ホームともにかなり貴重な一枚と言えるのではないだろうか。やはり、記録は残しておくものである。