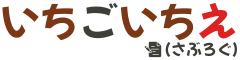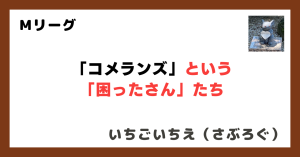はじめに
先日、訳あって積ん読にしていた『学び効率が最大化するインプット大全』(樺沢紫苑 著)を読んでいたところ、以下の著述が目に留まりました。
誰が書いているのかわからない記事は、情報としての価値がありません。なぜなら、信憑性の確認がとれないから。著者名、ライター名、サイトの主催者名が書かれていれば、その名前で検索すれば過去の実績や口コミはすぐにわかります。
引用元:『学び効率が最大化するインプット大全』(150-151頁)
本名で記事を書いている人は、嘘を書けば現実での名声に傷がつくので、責任のある文章を書く確率が高い。匿名やハンドルネームの人は、嘘を書いてもなんのマイナスにもならないので、信憑性は低くなります。
これは要するに「実名の方が言っていることは信用できるが、匿名の方が言っていることは信用してはいけない」ということです(と私は解釈しています)。しかし、およそ20年にわたって、名前や舞台を変えながらネットで活動を続けてきた私からしますと、そんなことはまずあり得ない、という思いにしかなりません。
「ネットの匿名性」は決してノーリスクではない
まず確認しておきたいのが、「匿名ならば何でもウソやデタラメを書いて良いはずはない」ということです。
いくら匿名だからと言っても、殺害予告をしたからということで、書き込みの際に保存されていたIPアドレス等が根拠となり、書き込んだ本人が逮捕された事例は枚挙に暇がありません。あるいは、自分の犯した失言や不法行為等がもとで、過去に公開した写真や発言により身元や実名などが割り出されてしまったケースも数多いところです。
こういったところから、「どんな場所であれ、完全な匿名性が担保されているとは言い難い」ということだけは言えます。何らかの要因により常に丸裸にされるリスクがあるということは知っておくべきです。
いずれにしても、たとえ匿名であっても、他人にひどく迷惑をかけるような真似だけはしてはいけません。
実名で書くときのリスクを理解しよう
最近、愛知県豊田市の元市議が、常磐自動車道における「あおり運転殴打事件」において、事件とは無関係の女性を関係者として仕立て上げた内容の発言をSNS上で拡散した、ということが大きな問題となりました。
【追記】 この方は情報を載せた当時こそ議員の身分でしたが、炎上の責任をとるために議員辞職しています。その後、名誉毀損のために女性から訴えられた後、示談等が成立することもなく敗訴しています。
この件については、後日、本人がきちんと謝罪をしたから良いのではないか、とする向きもあるのではないでしょうか。しかし、当該の拡散行為が軽率であったことは否定できませんし、何よりこの行為自体を取り消すことは不可能となっています。
実名で発言すると怖いのは、この「なかったことにはできない」というところです。匿名ならば、よほど過激な発言でもしない限りは、名前さえ変えてしまえば、自分の犯した過ちをなかったことにすることができます(本当なら猛省すべきところです)。
しかし、実名でやらかしてしまうと、「ああ、あのひどいことを言ったあの人ね」というようなイメージが紐付けされてしまい、下手をすると二度と社会の表舞台に立つことが不可能となってしまいます。当記事の趣旨からは少し外れますが、過去に「バイトテロ」を犯した当の本人が悲惨な人生を送る羽目になってしまったのは、良い教訓とすべきでしょう。
匿名ならば、失敗したときのリスクはそれほどでもありません。そのために、あることないこと言えてしまうのは確かでしょう(繰り返しますが、決してノーリスクというわけではありません)。一方、実名であるならば、一度失態をしてしまったというだけで、その当時の悪評が出回るようになります。失言をしたり失態を演じたりしたときのリスクがあまりにも大きすぎるのです。
そういうリスクがあることを理解した上で、「実名である分、責任のとれる発言しかしない」という自制をする人もいるにはいるでしょう。しかし、世の中、そういう人ばかりではありません。上の元豊田市議の事例もその1つです。
その他にも、例えばデヴィ夫人が無関係の女性を某自殺問題の関係者として仕立て上げた文章を写真付きで書いたのも大きな問題になりました。その他、実名だからといっても無責任なことをたくさん言っている人はいくらでもいます。そして、昨日まで責任ある人間だと思われていた人が、ある日突然、SNS上で無責任なふるまいを演じてしまうことさえあるのです。
上記の「バイトテロ」やデヴィ夫人の事件に関する詳しい情報は以下からどうぞ。
冷蔵庫に入りバイト先を閉店に追い込んだ学生 人生に悩み中|NEWSポストセブン
【衝撃事件の核心】裁判所に「非常に軽率」と指摘されたデヴィ夫人…ブログで「大津いじめ自殺」にモノ申し、アクセス急増も掲載写真は無関係な女性(1/4ページ) – 産経WEST
情報の「信憑性」に匿名も実名も関係ない
情報の「信憑性」を判断する上で重要なのは、何よりもまず、必要な手続きを行っているかどうかだと思います。データを示しているのならば出所を明らかにすべきですし、引用元や根拠を明示するなどというのは当然のことでございます。そして、何より大事なのは、他人を侮辱したりレッテルを貼り付けたりする発言は厳に慎んでおく、ということです。そして、万が一、虚偽の情報を載せてしまったならば、すぐに謝罪をすることが大事です。
匿名であっても、このようなことを遵守している方ならば尊敬に値する一方、実名であっても、守れていない人であるならば信用することができません。すなわち、日頃の行いが物を言うのであって、「信憑性」に匿名か実名かは全くもって関係がありません(あったとしても有意と言えるかどうかは微妙です)。
第一、仮に匿名であったとしても、ハンドルネームを採用している人であれば、活動期間が長くなればなるほど、過去の実績や口コミなどというものはすぐに見つかります。5chのような「名無しさん」であれば区別はつかなくなりますが、「ハンドルネーム」にはこのような効能もあります(気休め程度ですが)。
5chでも、一部スレッドで「強制コテハン」(通称「ワッチョイ」)や「強制IP表示」が導入されています。しかも、「スレ立て」時に指定の方法を行うだけで実現できてしまいます(板にもよりますが)。
これにより、特徴ある書き込みを行っている方の特定などが以前よりもかなり容易となっています。